はじめに ― ブログを刷新することになった理由
このたび、ブログの方針を刷新することにしました。
これまでは「抽象的な内容」を中心に記事を書いてきました。抽象的な話は応用がきき、幅広い場面で役立つ強みがあります。しかし、その良さを実感するには読む人に経験や慣れが必要で、多くの方にとっては「難しい」「どうすればいいのか分からない」と感じる部分もあったと思います。
そこで、これからは「もっと分かりやすく」「すぐに使える」記事を中心にしていきます。これは抽象的な考え方をやめるのではなく、「入口は具体的なブログ」「奥行きは抽象的な論文や書籍」という二層構造に整理する取り組みです。
抽象的な記事の良さと難しさ
抽象的な内容には良さと難しさがありました。
- 良さ:応用範囲が広く、どんな場面でも使える
- 難しさ:慣れていない人には分かりにくく、実用性が伝わりにくい
例えば「学びはインプットとアウトプットの循環」という考え方は、勉強にも運動にも使えます。しかし、そのままだと「じゃあ具体的に何をすればいいの?」と迷ってしまう人も出てきます。
抽象的な思考は、認知心理学で「流動性知能」と呼ばれる能力と深く関わっています。これは新しい問題を解く力や、目の前の状況からパターンを見つける力です。IQやワーキングメモリの高さと関係があり、得意な人ほど抽象を具体に落とし込みやすい傾向があります。一方で、この力に慣れていない人にとっては「抽象的な文章を理解して具体に変える」ことは大きな負担になります。
ブログは具体性を重視します
これからのブログでは「今日から使えること」を中心に書いていきます。
たとえば「暗記を助ける簡単な工夫」や「集中力を高める習慣」などです。こうした記事は読むだけでなく「とりあえずやってみよう」と行動に移しやすいのが特徴です。心理学の研究でも、人は具体例と一緒に学ぶほうが理解しやすいことが示されています。
具体的な記事を増やすことで、幅広い読者が自分に合った学びを取り入れやすくなります。IQや認知機能に関わらず、まずは「できることから始める」ことが重要です。行動の積み重ねは、やがて抽象的な理解につながり、後天的に知性を伸ばす基盤となります。
抽象的な内容は「論文や書籍」にまとめます
抽象的な考え方そのものは消えません。今後は「論文や書籍」といった形でまとめ、より丁寧に解説していきます。
そこでは、ブログで紹介した方法の裏にある理由を示します。たとえば「なぜアウトプットが記憶に効くのか」という問いに対して、脳や心理学の研究をもとに説明します。これは数学でいう「答えの証明」にあたる部分です。
また、論文や書籍はブログとは別のプラットフォームで公開する予定です。どの形を選ぶかは現在構想中であり、決まり次第あらためて告知します。有料記事やメンバーシップといった仕組みも視野に入れています。
Maksimのモデル変更について
今回の刷新では、記事の方向性だけでなく、登場キャラクター「Maksim」のモデルも見直しました。
これまでは短髪で幼い印象を基準にしていましたが、新しいモデルでは髪を肩にかかる長さにし、中性的で神秘的な雰囲気を強調しました。これは筆者自身の好みを反映しつつ、読者にとっても「安心感」や「知的さ」をより感じてもらえるように意図した変更です。
童顔の親しみやすさはそのままに、髪型や雰囲気を調整することで神秘的な印象を加えました。これにより、読者にとって「近づきやすさ」と「奥行きある知性」の両方を感じてもらえるモデルとなっています。
衣装や全体の軸(白を基調に紺と金の縁取り、静かで落ち着いた佇まい)は変わっていません。今後は新しいモデルを記事やイラストに反映し、刷新のもう一つのポイントとしてお伝えしていきます。
なお新モデル公開は、次回の記事にて行います。少々お待ちください。
過去記事について
これまで公開してきた抽象度の高い記事も、順次「具体性を高めた新しい記事」に作り替えていきます。
元の記事は、役割を終えた段階で随時非公開とし、必要に応じて精錬して論文や書籍としてまとめ直す予定です。こうすることで、読者の方にとって「読みやすく・使いやすい」形を維持しながら、奥行きを求める方には後日さらに深い内容を提供できるようにしていきます。
おわりに ― 新しいスタイルへ
今回の刷新は「抽象をやめる」ことではなく、「分かりやすさ」と「深さ」を分けて整理することです。
- ブログでは、実用性を重視した具体的な記事を
- 論文や書籍では、抽象的な理論や背景を
- モデルでは、童顔の安心感に神秘性を加えた新しい姿を
この三つの刷新で、より多くの人に届き、必要な人にはさらに奥行きを提供できるようにしていきます。
なお、このお知らせ記事も役割を終えた段階で非公開にする予定です。刷新の方針そのものが実際のコンテンツへと移行すれば、この告知は役目を終えるからです。


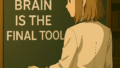
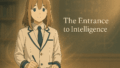
コメント