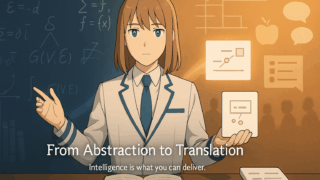 MENSA
MENSA 高IQ者が果たすべき本質的役割とは何か ——『抽象』から『翻訳』へ
抽象化する力だけでは知性とは言えません。それを翻訳し、渡すことのできる能力——これこそが現代において本当に求められている知性の姿です。訓練可能な三段階プロセスを解説します。
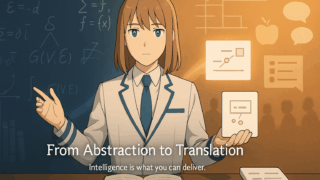 MENSA
MENSA 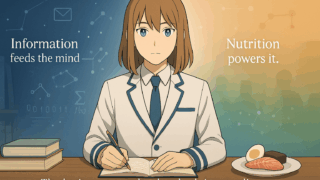 栄養学
栄養学 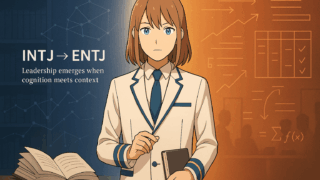 タイプ分類
タイプ分類  知性と構造
知性と構造 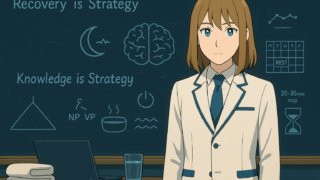 IQ・知能構造
IQ・知能構造 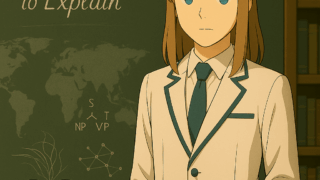 学習・能力開発
学習・能力開発 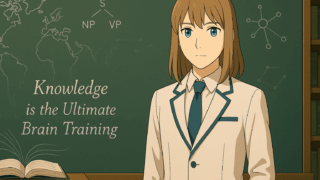 知性と構造
知性と構造 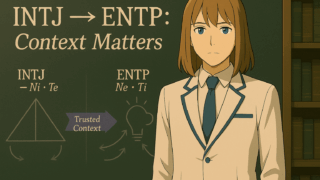 タイプ分類
タイプ分類 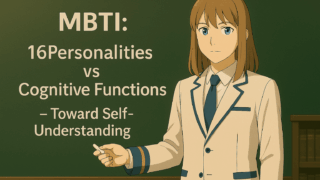 タイプ分類
タイプ分類