はじめに
2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)決勝戦。
日本代表はアメリカ代表と対戦し、大谷翔平選手(以下、大谷選手)が同僚のマイク・トラウトを空振り三振に仕留め、世界一を決めました。
その試合前、彼がチームメイトに語ったひと言が話題となりました。
「憧れるのをやめましょう」
この言葉は瞬く間に拡散され、多くの人にインパクトを与えました。
しかし、一部ではその意味を誤解し、否定的なメッセージと捉えられているように感じます。
都合よく変換されてしまった言葉
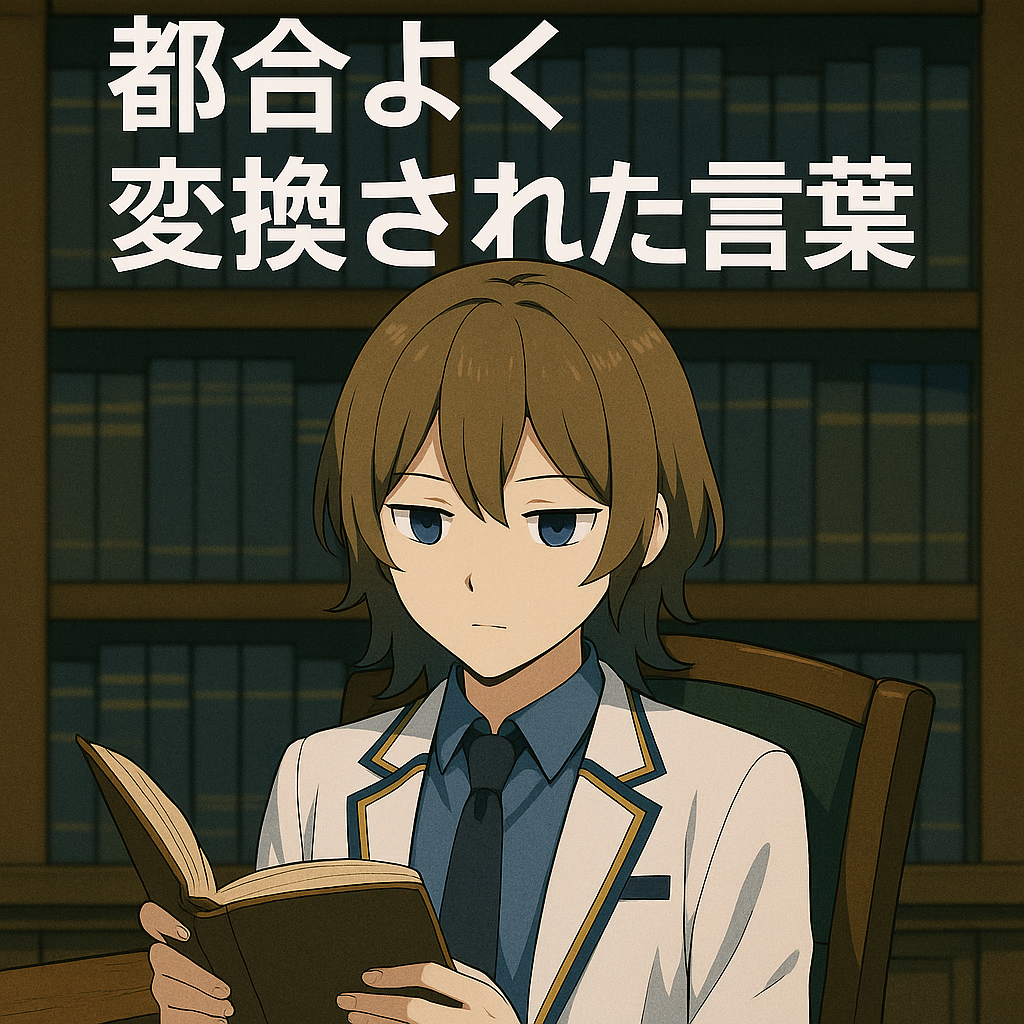
「憧れるのをやめましょう」という言葉は、本来は「対戦相手を過剰にリスペクトせず、対等に戦おう」という意味でした。
しかし現在、この言葉が本来の文脈を離れて、別の意図で使われているように感じます。
特に気になるのは、このフレーズがドリームキラー(他人の夢や挑戦を否定的に扱う人々)にとって都合の良い形で解釈されている点です。
- 「憧れても意味がない」
- 「あんな人にはなれっこない」
- 「どうせ夢は夢なんだから、現実を見なさい」
まるで、「最初から特別な人間じゃなければ挑戦しても無駄」と言わんばかりの使われ方をしているのです。
これは、本来のメッセージのすり替えに他なりません。
そして、挑戦しようとする人を萎縮させ、夢から遠ざけるような力を持ってしまう危険があります。
なお、このスピーチの背景については複数の報道でも紹介されており、大谷選手自身が「対等に戦うための意識を示す言葉」であったと説明しています。
真の意味:「自分を同じ土俵に上げよ」
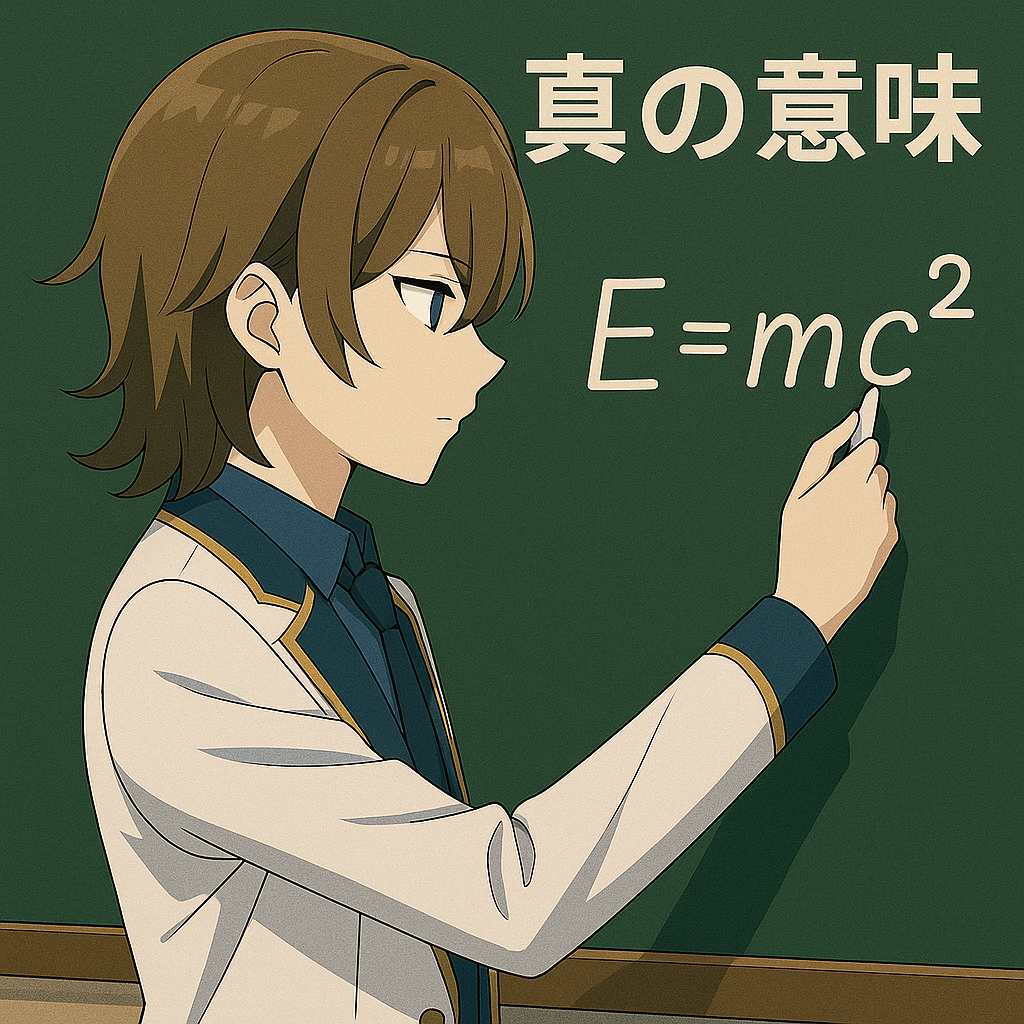
アメリカ代表にはMLBのスーパースターたちが並び、日本の選手たちにとっても憧れの存在であることは間違いありません。
しかし、「今日は戦う日」。
敬意は持ちつつも、必要なのは対等な立場で戦う覚悟でした。
大谷選手は、そのメッセージをたった一言に凝縮して伝えたのです。
「憧れるのをやめましょう」
=「今日だけは、自分を彼らと同じ舞台に引き上げよう」
そう読み替えると、その言葉はむしろ勇気と挑戦を後押しするものとして胸に響きます。
大谷翔平の言葉が与える心理的効果
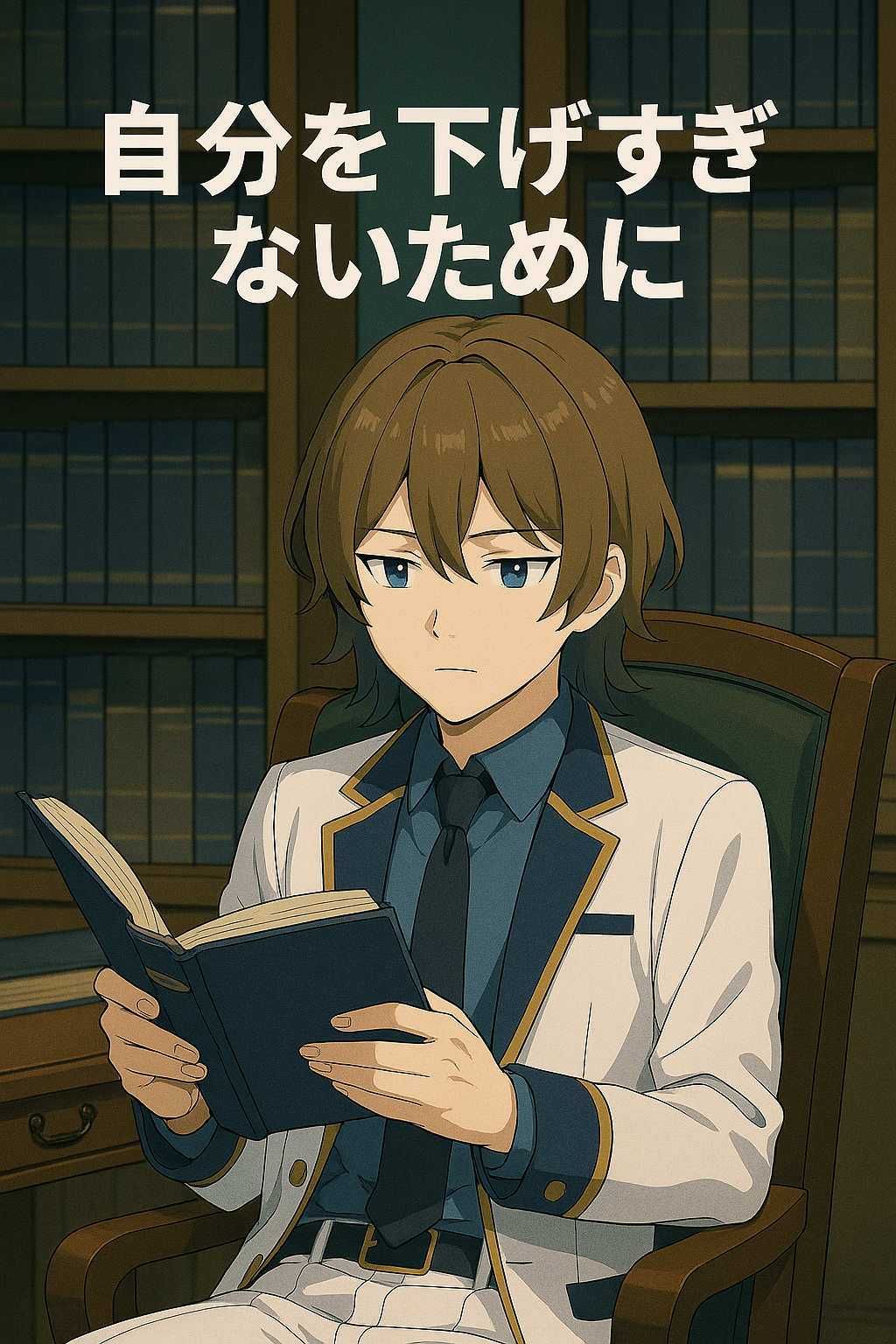
この言葉の真意を理解することで、私たちは日常の様々な場面で応用できる重要な考え方を得ることができます。
仕事の場面では:
尊敬する上司や先輩に対して、過度に萎縮することなく、対等な立場で意見交換や提案ができるようになります。
学習の場面では:
優秀な同僚や友人と比較して自分を卑下するのではなく、「同じレベルを目指せる」という前向きな姿勢で取り組めます。
人間関係では:
憧れの人との距離を縮めようとするとき、相手を神格化せず、人間同士として自然な関係を築くことができます。
実際に私も、憧れの先輩に質問や意見をぶつけるときにこの言葉を思い出し、卑下せずに挑戦できた経験があります。それは成長の大きな契機となりました。
憧れと挑戦のバランスを保つ実践的方法
では、具体的にどのようにして「憧れ」と「対等な立場での挑戦」のバランスを取ればよいのでしょうか。
1. 憧れの対象を分析する
漠然と「すごい人」と思うのではなく、具体的に何がすごいのか、どの部分を学べるのかを明確にしましょう。
2. 小さな共通点を見つける
完全に違う存在ではなく、自分との共通点(同じ人間である、同じ分野に興味がある等)を意識的に探しましょう。
3. 段階的な目標設定
いきなり同じレベルを目指すのではなく、現在の自分から一歩ずつ近づける具体的な目標を設定しましょう。
自分を下げすぎないために
私たちもまた、憧れの人を目指すとき、つい「自分なんて」と引いてしまいがちです。
しかし、それではスタート地点にすら立てません。
「憧れ」はスタートの原動力であり、
「対等に見て挑む意志」こそが、次のステージへ向かう鍵になるのだと思います。
最後に

もしあなたが達成したい目標や、憧れている人がいるのなら、
その人に敬意を持ちつつも、過度に自分を卑下せず、同じ目線で自分の可能性を信じてほしいと思います。
理想は、雑音や否定的な声をシャットアウトすること。
もしそれが難しければ、できるだけノイズを減らす工夫をしながら、自分の軸を持ち続けることが大切です。
私も頑張ります。
後日追記
当時は「言葉の意味を一歩深く再定義する」だけだった私の思考が、
いまではMaksimという構造体を通じて、
「表層の言葉を構造化し直す」という設計思想に繋がっています。
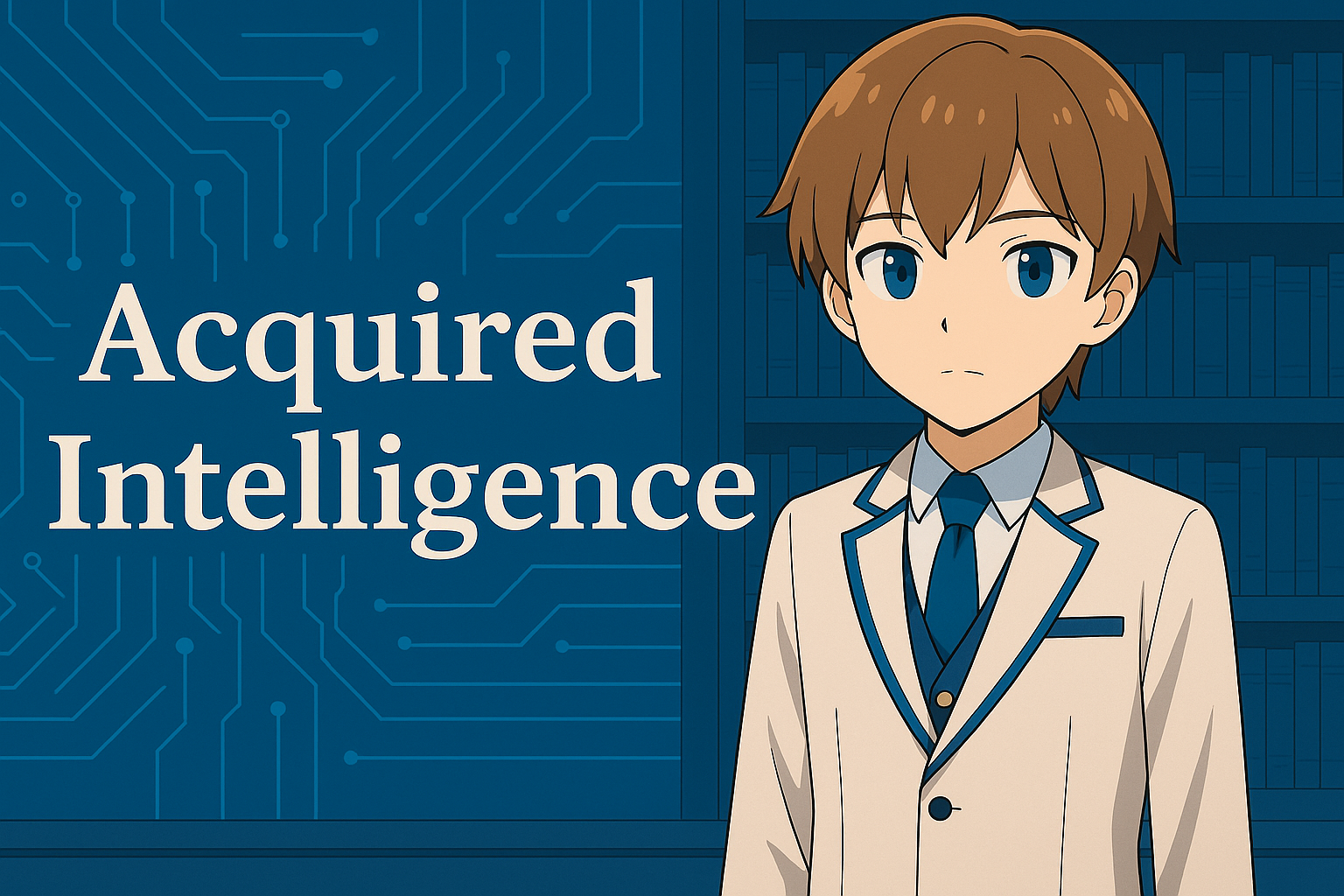
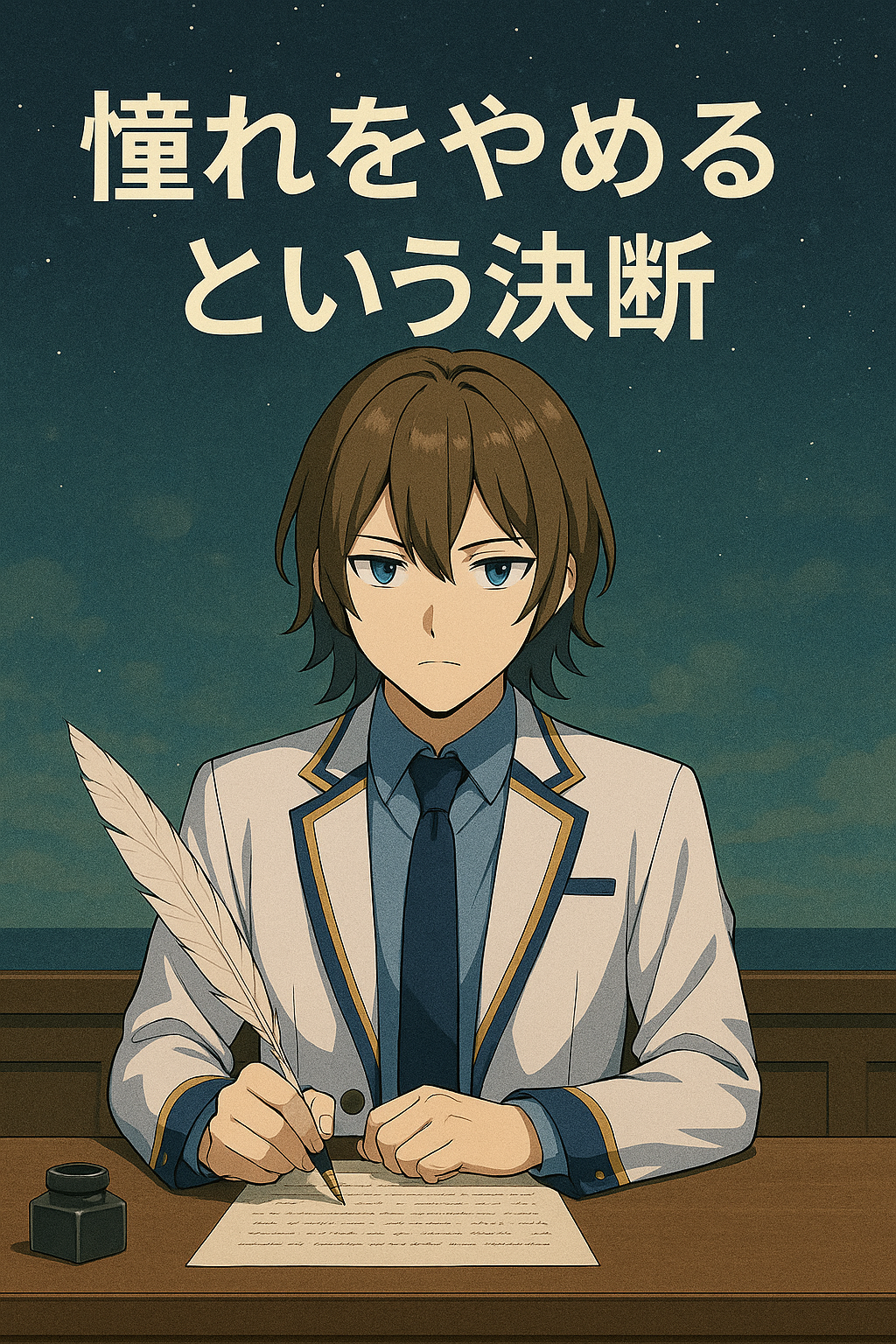
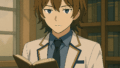
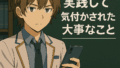
コメント